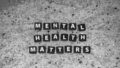衛生管理者や産業医の選任義務と同様、常時50人以上の労働者を使用する事業場にストレスチェック制度の実施義務があります。2015年12月から開始されたこの制度は、年1回この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられています。(この場合の「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。)
ストレスチェックの目的として、社員個人が自分のストレスを把握して対処する一次予防と集団分析による職場環境改善があります。ストレスチェックの集団分析を活用することで、組織全体や部署ごとのストレス状況を把握し、職場環境の改善やメンタルヘルス対策に役立てることができます。以下のような具体的な活用方法があります。
1. 組織全体のストレス状況の把握
ストレスチェックの結果を集団分析することで、組織全体のストレスレベルやメンタルヘルスの傾向を把握できます。たとえば、以下のような指標を確認できます。数値化することで、関係者の理解も得られやすくなります。
- ストレスの高い部署、年代、職位の把握
- 仕事の負担感や、上司だけでなく同僚との人間関係、ハラスメントの問題点の可視化
- 組織全体のストレス要因の分析(例:長時間労働、業務負荷、キャリア形成など)
2. 職場環境の課題の特定
集団分析を行うことで、職場のストレス要因を特定し、改善に向けた具体的な施策を立案できます。例えば、以下のような課題が浮かび上がることがあります。
- コミュニケーション不足によるストレス → 月1回の全体ミーティングや相談体制の構築などチームビルディング施策の導入
- 過重労働の影響 → 業務分担の見直しや労働時間管理の強化
- ハラスメントリスク→ 相談窓口の設置や研修の実施
3. 施策の効果測定
ストレスチェックの結果を継続的に分析することで、導入した施策の効果を測定し、PDCAサイクルを回すことができます。職場環境改善の取り組みへのストレスチェックの活用には以下の資料も参考になります。
東京大学 職場環境改善の手引 https://mental.m.u-tokyo.ac.jp/old/1595.pdf
労働者健康安全機構 職場環境改善スタートのための手引き https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/material/download/R5_syokubakaizen2.pdf
4. 健康経営や組織の活性化への活用
ストレスチェックの集団分析は、健康経営の指標として活用でき、企業の生産性向上や従業員エンゲージメントの強化につながります。
- 健康経営優良法人の認定に活用
- 社員のエンゲージメント向上の施策策定
- 離職率低減や職場満足度の向上
5. 産業医・カウンセラーとの連携
集団分析の結果を産業医やカウンセラーと共有し、適切な対策を講じることができます。具体的には、以下のような活用が可能です。
- 高ストレス部署に対するヒアリングの実施
- 職場改善提案の検討
- 健康管理部門との連携によるサポート強化
6. データに基づく経営戦略への反映
ストレスチェックの集団分析データを活用し、職場環境改善を経営戦略の一環として取り入れることも可能です。
- 組織風土改革の方向性を決定
- 働き方改革の推進
- 人的資本経営の一環としての活用
まとめ
ストレスチェックの集団分析は、単なるデータ収集ではなく、職場環境の改善やメンタルヘルス対策、さらには経営戦略に役立てることができます。結果を適切に活用し、従業員が働きやすい環境づくりを進めることが重要です。職場と産業保健専門職とのコミュニケーションにより、集団分析結果の解像度が高まりますのでぜひ専門家を活用してください。